こんにちは。
今回は一級建築士製図試験に向けて僕が実際に試した製図用道具を紹介していきたいと思います。
製図を素早く書くためには何といっても作図中に悩まないことです。
これはプランニングだけでなく道具についても言えることができます。
この線を引くときはこの道具、ここはフリーハンドで描く、、、
巷にあふれている速記法をそのまま真似するだけでなく実際に自分で試し、自分だけの作図法を身に着けてほしいと思います。
ここで、紹介するのも参考になればと思います。それでは、まずは定規編です!
三角スケール
まずは三角スケールを紹介していきます。
便宜上、三角スケールと書いていますが、最終は三角スケールではなくなりました(笑)。
はじめに
三角スケールは大小2つ用意しておくことをおススメします。
大きい三角スケールは通り芯の目印をつけるため、小さい三角スケールは間仕切り壁芯の目印をつけるために使用しました。
最初の道具
一番最初に使っていたものはいわゆる三角スケールです。
学生時代の製図道具をそのまま使っていました。
しかし、この一般的な三角スケール、時間を争う製図試験で使おうとすると以下のようなでめいっとがあります。
- のぞき込まないと目盛りが読みにくい。
- 使いたい縮尺を探す手間がかかる。
三角スケールはその名の通り三角形になってますので、目盛りを読む際少し前のめりになりのぞき込む必要がありました。
普段仕事でたまに使う際にはあまりに気になりませんでしたが、やはりスピード勝負の一級建築士製図試験。
このひと手間すごくストレスが溜まりました。
そして、皆さんも経験あると思います。目的の縮尺を探すために三角スケールをくるくる(笑)。
分かっているものの同じ面に1/100、1/200が並んでいる三角スケール1/100の次はつい回転させ1/200を探してしまします。
これもいつまでもなれることがなく焦りを生む原因となりました。
製図試験に臨んだ三角スケール
冒頭で最終的には三角スケールは使わなくなったと書きましたが、最終的にはこの定規を使うことになりました。
ウチダ ヘキサスケールです。
この商品の30cmと15cmで最終的に製図試験に臨みました。
- 三角スケールのすべてのデメリットを解消
まず、平定規になってますのでのぞき込む必要がなくなりました。
そしてこのヘキサスケールは縮尺が1/100、300、500が同じ方向を向いており、ひっくり返すと1/200、400、600となります。
つまり片面は奇数、片面は偶数と並んでいるのです。
三角スケールのわずらわしさに悩み、ネット検索しまくっていましたが、この商品との出会いは最高でした。
製図試験が終わった今でもこのヘキサスケールは愛用し続けています。
三角定規
次に紹介する定規は三角定規です。
ここでの三角定規は通り芯を引くための大きな直角定規を指します。
僕の場合、三角定規は縦の基準線を引いたらお役御免となる開始5分でしか現れない奴でした。
たった序盤5分のためでも、必要な道具は揃える。
それが、製図試験です。
製図試験に臨んだ三角定規
いきなりですが、製図試験に臨んだ三角定規です。
僕は学生時代から使っていたステッドラーの製図用三角定規30cmを使用していました。
ちなみに二等辺三角形の定規は使いどころがありません。横の線は製図板の平行定規を使います。
おすすめの三角定規
僕は買い替える必要はないと感じたので学生の頃使っていたものをそのまま使用していましたが、デメリットはありました。
- 縦の基準線を一気に引くことができるか
製図試験の用紙はA2サイズです。
僕が受験したときはその中に3つの平面図と1つの断面図そして面積表を書き込みます。
つまり平面を縦に並べて各必要があります。
いちいちスケールで目安を付けることはせず縦の基準線は一気に引きたいものです。しかし、30cmの定規では一度、平行定規を下げる必要があります。
そこで、おススメしたいのは36cmの三角定規です。これであれば縦の線を一気に引くことができます。
テンプレート
はじめに
テンプレートは柱型、梁型、衛生器具、家具などを描くために使用します。
最終的には使い道は、
- 平面図における柱型
- 断面図における柱幅・梁幅の基準線
となりました。
衛生器具や家具ではテンプレートは利用していません。
楕円形の丸や便器の毛状などはフリーハンドで描くようになりました。
また、断面図における基準線に使う方法は、動画サイトで見つけた方法を採用しました。
一度、動画サイトで「製図 速記」などで検索してみてもよいと思います。
さすがに当時参考となった動画は見つけることはできませんでした、、、
使う目盛りに印をつけるなど現在の試験では使えないものもありますが非常に参考になります。
試行錯誤のテンプレート
まず、勉強を始めてすぐは他の道具と同じで学生時代に使用していたものを使っていました。
一般的な丸・三角・四角のテンプレートです。
しかし、この商品製図試験に臨むものとしてはおススメしません。買わないでください(笑)。
- 薄くてつかみにくい
- 使わないものものがたくさんある
- テンプレート意外に使い道がない
製図試験はやはり時間との勝負です。
薄くて単純に掴みにくいものは、それだけでイライラしたり、焦ったりといいことはありません。
また、先ほど三角定規の時には、基準線を引く専用の道具として紹介しましたが、テンプレート定規においてはテンプレートを書くためだけの道具では使い物になりません。
それは、使用するタイミングが仕上げ作図時になるからです。
仕上げを書くタイミングでは、壁の線を引きながら家具等を記載したりしていきます。
したがって、専用道具としていちいち、定規を交換している必要がありません。
まずは、学生時代使っていたものを使うかと思って、テンプレートを用意しましたが、製図試験に向けた勉強をはじめてすぐにその使いにくさに気づき、別物を買いあさりました。
そこで、Amazonで検索して真っ先にでてきた、以下のテンプレートを購入することにしました。
柱型等のテンプレート要員だけでなく壁線などメインの作図定規とも兼用したくなったためです。
しかし、この定規でも描けなくはありませんでしたが、三角定規である必要はないし、もっと使いやすいものはないかと探しました。
製図試験に臨んだテンプレート
最終的には、以下のサイトで販売しているオリジナル商品を使うことにしました。
最端製図オンラインショップより画像引用
最端製図 ONLINE SHOP
「最端製図.com」という二級建築士 製図試験のサポートサイトになります。
このサイトの「学習アイテム」のタブから「テンプレート定規1/200」を購入しました。
厚さ2mmで四角形のテンプレート定規です。
他の定規と比べると割高ではありますが、作図スピードアップには非常に有効なものでした。
- 四角、丸、楕円 必要な図形がそろっている
- 目盛りが1/200であるため、簡易的なスケールとしても使える。
- 四角形であるため縦、横の線を引くことができる
僕は2.の縦にも1/200の目盛りがあることで、この定規にしてから断面図の描く順序を替えることにしました。
スケールは、ヘキサスケールを基本使用していましたが、横線を引くための目盛りはスケールを縦にして断面階高用の目安をつける必要があり、ヘキサスケールでは、縦横比が大きく不安定で不便でした
この定規になったことで、平面図を文字を残し完全に描き終えてから断面図の作図をするようになりました。
3.横の線は平行定規で引くのではないかと思う方もいるかもしれませんが、平行定規にこのテンプレートを載せ、横の線を引くようになりました。
また、上記の三角定規と違って縦の線が左右どちらでも引けることもたまに役に立ちました。
一級建築士の試験は1/200で作図します。
上記サイトは二級建築士を対象としているため、1/100のテンプレート定規も売っています。
間違って1/100を買わないように注意してください。
メイン定規
メイン定規は3.テンプレートで書いた通り、最終的には兼用しましたので特に書くことはありません。
最初は普通の算数などで使うような小さい三角定規を使っていました。
その他
その他として、定規に関連するアイテムを紹介しておきます。
フローティングディスク
フローティングディスクです。
なんてことはありません。ただ定規の滑りをよくするため片面がアルミになったシールです。
これを定規の隅3箇所程度に貼ってました。
絶妙な厚さでシャーペンの芯が定規の下に入り込むこともないし、滑りが良くなることで作図スピードのアップ、図面のきれいさを保つことができます。
僕の場合4箇所貼ると製図板の傾斜だけで定規が滑ってしまう問題が発生しましたので3箇所としています。
テープが強力なのど一度貼り、はがしてしまうと痕が残り、逆に図面を汚す要因にもなると思います。一つ貼っては滑りを試し、最適な数を見つけてください。
定規に取っ手をつける
僕はこの方法行ってません。
それは三角形のテンプレート定規を使っている時に取っ手のある商品で、持ち上げは確かに楽でしたがテンプレート使用の際に邪魔に感じたからです。
こればかりは好みの問題かと思います。どちらが使いやすいか一度試してみたはいかがでしょうか?
また、取っ手付きの定規をわざわざ探さなくても、平ゴムとかを自分でくっつけてみてはいかがでしょう。僕の友達はガラスの下に入れるセッティングブロックをもらってそれを定規に付けてました。
まとめ
いかがだったでしょうか。一級建築士製図試験に向けての道具紹介。
本試験まで時間がない中ではありますが、製図道具はいろいろ試し、自分に合ったものを使うことが最終的に作図の時短にもつながります。
最後に、僕の好きな漫画の名言から
レースに負けたら機材を疑え レースに勝ったら自分を讃えろだぜ?
巻島裕介(弱虫ペダル)
レースに臨む前にまず、道具に頼りましょう。
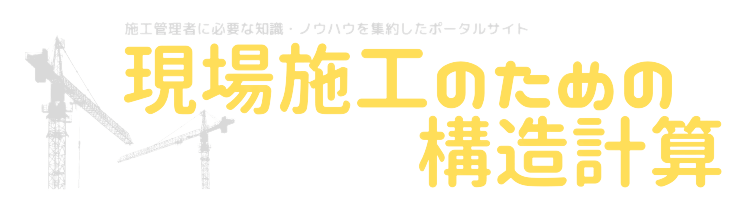







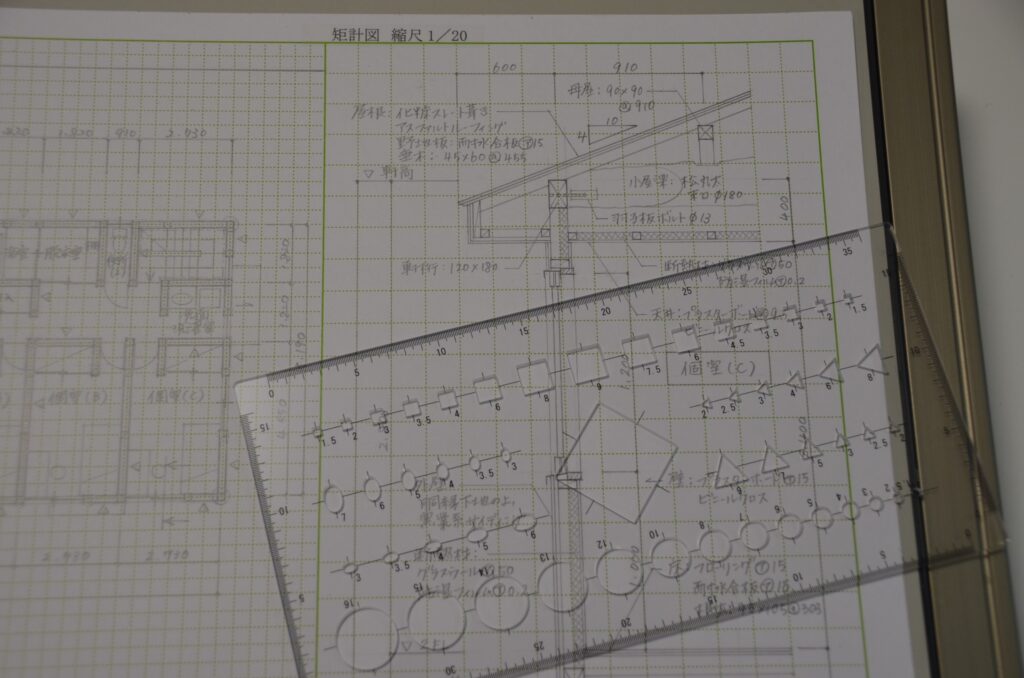


コメント