建設工事では、建物への入り口となる歩道を切り下げして車が入れるようにする道路加工工事があります。
道路加工工事は、建物が完成してからの入り口を作るためのほか、工事中における工事車両の動線確保を目的として、施工者都合による工事が行われることがあります。
今回は、現場監督が実際に申請、協議を行う必要がある工事中における道路加工工事申請において申請から切り下げ工事完了までの一連の流れを説明していきます。
道路加工工事申請の流れ
まずは、道路加工工事の一連の流れは以下のようになります。
- 事前相談
- 道路加工申請
- 道路使用申請
- 道路加工工事着手届
- 道路加工工事
- 道路加工工事完了届
- 維持、保全
- 復旧のための道路加工申請
道路加工申請は、道路管理者に対して行います。県道、市道、私道などによって、道路管理者が変わってくるのでどこに申請が必要かは事前に把握しておく必要があります。
ここでは、私が実際に提出した市道の道路加工申請について説明していきます。
同じ市道でも自治体よって対応が異なったり、交通量など道路事情によっても対応が異なることになりますので、ご注意ください。
先に、道路加工工事の名称と通称を紹介しておきます。これらの言葉は工事現場では同じものを指していますが、様々な呼ばれ方をしています。
道路加工工事は、道路を加工するすべての工事のことです。道路の切り下げやインターロッキングブロックの補修、維持保全に係る工事など公共物である道路に対しする工事全般のことを指します。
切り下げ工事とは、道路加工工事の一種で、車道と歩道を分離する縁石などを撤去して、歩道を車道に対して、擦り付けるように加工する工事のことです。
現場で行う道路加工工事としては、切り下げ工事やインターロッキングブロックの撤去工事など限られた加工工事であることがほとんどですので、施工側の便宜上、実際の工事の名称で呼んでいます。
自費工事とは、道路などの公共物に対する工事を建築主や施工会社の自己負担にて道路加工工事をすることを指しています。
建設工事に伴う道路加工工事は、ほとんどが自費工事になりますので、道路切り下げ工事のことを自費工事と呼んでいる現場監督も少なくありません。
それでは、道路加工工事の申請から工事までの手順を紹介していきます。
道路加工事前相談
何事もそうですが、いきなり申請を提出するのではく、事前に相談に行くことがベターです。
道路の切り下げについては、切り下げの箇所数、幅など道路法や各自治体の条例によって決目られている場合がほとんどです。
ただ、建設工事に伴う道路加工は、建設工事後復旧することを条件に特例として認められることもあります。
なんでもOKというわけではありませんが、工事に必要な出入り口であれば、まずは相談に行ってみましょう。
相談に行く際は、対象の道路の場所や工事の計画がわかる資料を事前に用意しておきましょう。
- 対象の道路名称
- 縮尺1/5000程度の現場近況がわかる図面
- 道路加工範囲を示した総合仮設計画図
- 道路加工工事と切り下げ状態の期間を示した工程表
道路加工工事申請
事前相談で、道路加工についておおよその合意が取れたら、いよいよ道路加工工事申請を提出しましょう。
事前相談でどこまで、合意できているかにもよりますが、道路加工工事の2週間~1か月前には申請書を提出しておくようにしましょう。
実際に提出する自治体によっても異なってきますので、提出時期は事前相談時に確認しておくとよいでしょう。
申請する際には、所定の道路加工にともなう申請書と事前相談のときにも作成したような添付資料を作成する必要があります。
道路加工申請書
道路加工申請は、「道路工事等承認申請書」や「道路加工施行承認申請書」といった名称の自治体によって定められた書式(ここでは、道路加工工事申請書と表記します。)がありますので、まずはその申請書を自治体HPなどからダウンロードして記載します。
道路加工工事申請書の記載内容は、「工事の目的」、「道路の名称」、「工事の場所」、「対象となる面積」、「工事の期間」などになります。
必要な添付資料
必要な添付資料は自治体によっても異なりますが、事前相談でも作成した資料のほかにも加工後の道路の構成がわかる資料や周辺工作物との関係がわかる資料が必要になりました。
事前協議時に用意したもの
- 対象の道路名称
- 縮尺~1/5000程度の現場近況がわかる図面
- 道路加工範囲を示した総合仮設計画図
- 道路加工工事と切り下げ状態の期間を示した工程表
新たに計画・作成したもの
- 道路加工後の道路横断面、縦断面図
道路の構成は、基本的には現状の道路にならう構成とする必要があります。
アスファルト舗装の厚さ、下部砕石の厚さなど断面構成がわかるものを用意しましょう。
道路使用申請
道路加工するための申請は、無事完了しました。
ただ、道路加工のためには、一時的に道路を封鎖したり、う回路を設ける必要があります。
そのため、所管警察署に道路使用許可申請を行う必要があります。
使用許可は警察署と相談・申請場所が異なりますので注意しましょう。
道路使用許可申請は、所管警察署のHPから申請書をダウンロードして、さらに添付資料として、道路加工工事中の計画図を作成しておきましょう。
加工工事中にう回路は設けるのか、車道と仮歩道の区画はどうするのか、ガードマンは配置するのか、夜間などの工事時間外は仮開放するのかなど歩行者等の安全確保をイメージしながら資料を作成するようにしましょう。
また、道路使用許可申請には、手数料の納付が必要です。
道路加工工事
道路加工工事申請、道路使用許可申請ふたつの申請がおわりいよいよ道路加工工事が始まります。
ただし、その前に必要な提出資料がもう一つあります。
それは、道路加工工事着手届になります。
こちらは道路管理者に提出する書類で、道路加工工事を行う3日前までに届け出が必要です。
すでに、道路加工許可は下りていますので、道路加工申請時は〇月〇日~〇月〇日までと範囲を持たしていた工事期間を工程調整等し、実際に工事を行う3日前にお知らせを行うという目的が大きいです。
道路加工工事中は、歩行者等に気を付け、安全に工事を進めてください。
さて、道路加工工事が完了して、歩道を開放しました。
またここでも道路管理者に提出が必要な書類があります。
それは、「道路加工工事完了届」です。
道路加工工事完了届は、道路加工工事が完了次第、速やかにと提出時期が定められています。
こちらの書類も忘れずに提出しましょう。
維持保全
自費工事によって、切り下げを行った道路はその申請の責任で維持保全を求められることがあります。
特に、建築工事における道路切り下げを行った場合、通常の切り下げより幅が広くなったりもしますので、違法路上駐車などが起きる可能性もあります。
必要に応じて工事時間外はカラーコーン設置するなど対応を取りましょう。
また、工事中は、大型車両が頻繁に出入りします。そのため、アスファルト舗装がすぐに傷んだりしてしまう場合はあります。
不陸がおおきくなり、歩行者等の通行の妨げになってはいけませんので、必要に応じてアスファルト舗装の打ち直しなど道路の維持に努めるようにしましょう。
おわりに
道路加工工事の一連の流れを解説しました。
道路加工工事は、道路状況によって許可が下りるかどうかわからない点が多くあります。
また、提出すべき書類や協議を行う諸官庁、自治体も複数あります。私もはじめて道路加工申請をする場合は、相当苦労しました。
「自治体としては特段条例は設けておらず、基本は県の規定に従ってます。」といった回答があった自治体もあったり、ホームページ検索しているだけでは見つけることができない情報もたくさんありました。
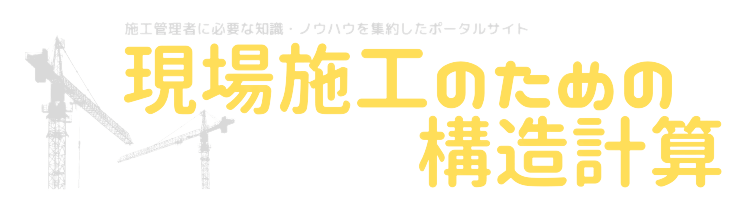
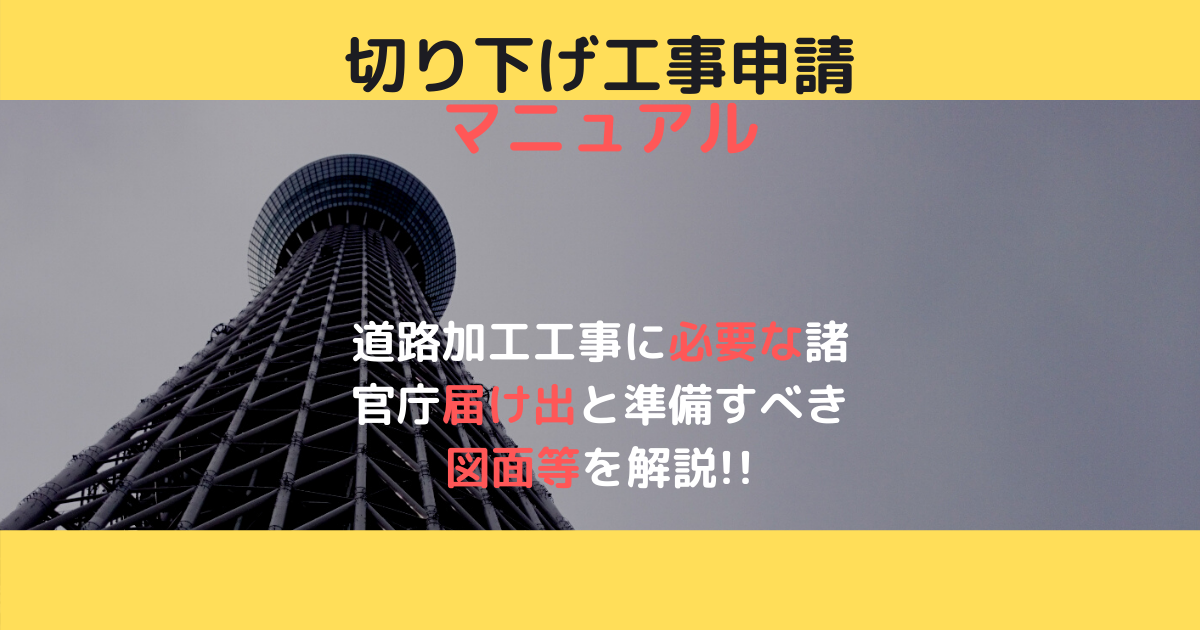


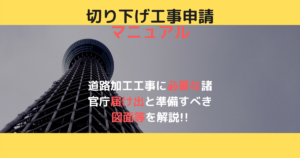
コメント