現場で作成する強度計算書
建設業では、設計者による建物の構造計算書だけでなく、施工者が自ら作成する強度計算書も多く存在します。
代表例として、足場・仮囲い・型枠支保工などの仮設物が挙げられます。
これらの計画では、一定規模や条件を超えると労働基準監督署への届出が必要になるケースもありますし、仮に届け出の提出が不要であったとしても施工計画を定める上で計算書の作成は必要不可欠です。
また、仮設物以外でも、施工上の都合で建物(本設)の一部を変更したい場合など、施工者側が強度計算書を作成して設計者・監理者と協議する場面も少なくありません。
つまり、施工管理の段階でも「強度計算書による裏付けと根拠を持った施工計画の立案」が求められています。
計算書をどう作るか
現場で強度計算書を作成する場合、一般的には次のような方法があります。
- 自分(作業所)で作成する
- 社内の技術支援部門に依頼する
- 協力会社や専門業者に依頼する
どの方法を選ぶ場合も、まずは使用部材や施工条件を明確に提示することが基本です。
施工計画者が主導して「どのような仮設材を、どんな条件で使うか」を整理した上で、計算書の作成を進める必要があります。
足場強度計算を例にする
足場の強度計算書と一口に言っても、必要な計算書はいくつかあります。施工計画に応じてどの計算書を作る必要があるかは、施工者が理解していないといけません。代表的なものは以下の通りです。
- 鉛直荷重に対する支柱(ジャッキベース・梁枠)の強度計算
- 風荷重に対する壁つなぎ金物の強度計算
- 荷受け構台や支保工の設計
計算書の作成では、施工条件を伝達しないと計算書の作成ができないものお送りあります。
壁つなぎ金物の計算を例にするとRC造の建物で壁つなぎの設置位置梁レベルによって決まってくるでしょう。S像であれば、胴縁が固定されているのであれば比較的融通が聞くかもしれませんが、外装パネルの目地によって決まるということもあるでしょう。
こうした施工条件を踏まえた入力が、正しい計算書を作る鍵になります。
強度計算書の作成方法
実際に足場などの強度計算書を作成する方法は一般的にはExcelで作成するか専用ソフトの利用やWEBサービスの利用になってきます。
Excelで作成する場合
最も一般的な方法です。
計算式を組み込み、パラメータを入力して算定を行います。
ネット上にもテンプレートが多数あります。
ただし、“計算ツール”ではなく“提出できる計算書”に仕上げることが重要です。
- 他人が見ても計画内容を理解できるか
- 参考文献・設計基準の出典が明記されているか
- 労基署提出に耐えうる書式になっているか
計算ソフトを使用する場合
仮設構台・支保工などには専用の市販ソフトもあります。
入力項目を設定するだけで自動で算定結果が出力される便利なツールです。
一方で、費用面・操作難易度・導入コストが課題。
現場単位での導入は少なく、社内技術部や専門会社が使用するケースが多いです。
おすすめのツール
強度計算書作成Webアプリ『Calku』
最近は、Excelや高価なソフトに代わって、Web上で計算書を作成できるサービスも登場しています。
その代表が Calku です。

Calkuは、足場や仮設物などの施工時に必要な強度計算書をブラウザ上で作成できるWebアプリ。
Excelのような自由度と、ソフトのような自動化を両立しています。
- 入力項目を選ぶだけで提出用フォーマットの計算書を自動生成
- 計算内容の解説付きで理解しながら作成できる
- Web上で共有しやすく、社内での確認も容易
- 計算書の作成として、無料で試すことができる
- Excelに慣れた人には操作感が異なる
- 一部機能(共有・PDF出力など)はベータ版段階
Excelテンプレートの紹介
本サイトでも足場強度計算書のExcel版テンプレートも用意しています。
パラメータを入力するだけで提出レベルの計算書を作成可能です。
- 使い慣れたExcel環境で編集可能
- 一度購入すれば繰り返し利用可能
- 入力内容を理解していないと誤算につながる
- Excel関数を壊すリスクがある
- 法改正対応があった場合は、買い直しが必要または自己責任
強度計算書の作成依頼
ここまで、強度計算書を作成するためのツールとして
Excel・計算ソフト・Webサービスといった方法を紹介してきました。
では次の、実際に誰がその計算書を作成するのかという点を考えていきます。
作業所内で自ら作成する
現場の施工管理者が、直接ExcelやWebアプリを使って自ら計算書を作成する方法です。
計算書の作成方法が理解できてれば、最もスピードが早く、施工計画の変更にも柔軟に対応できるでしょう。
設計条件や現場の納まりを把握しているのは現場自身であるため、修正や各種パターンが厳格な計算書の作成など施工系カウに沿った計算書を作成することができます。
一方で、構造力学や荷重計算の基礎を十分に理解していないと、誤った前提や単位の使い方で計算ミスが生じる可能性があります。
また、現場管理をしながら、提出レベルの計算書をフォーマットを意識して作成するハードが非常に高いです。監理者や第三者が確認する際に、「根拠の明示」「出典の明記」が不十分だと再提出を求められることも少なくありません。
社内の技術支援部門に依頼する
社内に技術支援や品質管理といった部門があれば、こういった部署に依頼することが手っ取り早いでしょう。
また、計算書を作業書で作成して、そのチェックを依頼すると言うことも可能です。
私自身もこのような技術支援部門に所属していましたが、一般的な計算書は計算ソフトを利用して、計算ソフトで対応できないような特殊な計算も柔軟に行うということを対応してき巻いた。
また、現場との意思疎通も比較的容易で打ち合わせや不明な点があれば直接現場に伺って対応ということも柔軟にできます。
専門施工会社や協力会社に依頼する
社内に技術支援部門を持たない場合は、真っ先に検討する依頼先として協力会社になるでそう。
足場であれば仮設リース会社や専門施工会社である鳶工など対応できるか相談してみてもいいでしょう。
ただ、協力会社も実際にはそこからさらに外注したりということも多いです。
そのためデメリットとしては、施工計画を十分に伝えきれない可能性があるということです。
多くの場合、計算書の作成は修正〇〇回まで定めている場合が多いので、計算結果がでてから何度も修正するとラリーに時間も要しますし、余計な費用も発生してしまいます。
おわりに
強度計算書は「提出義務があるから作る」ものではなく、施工の安全性を裏付ける技術資料です。
どんなツールを使うにせよ、現場担当者自身が内容を理解しておくことが重要です。
計算結果を“読む力”があれば、現場での判断スピードも確実に上がります。
ExcelでもWebアプリでも、自分に合った方法で根拠ある施工計画を進めていきましょう。
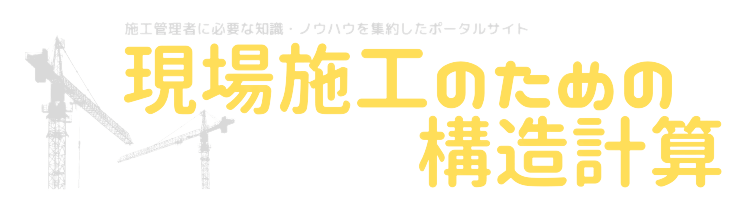
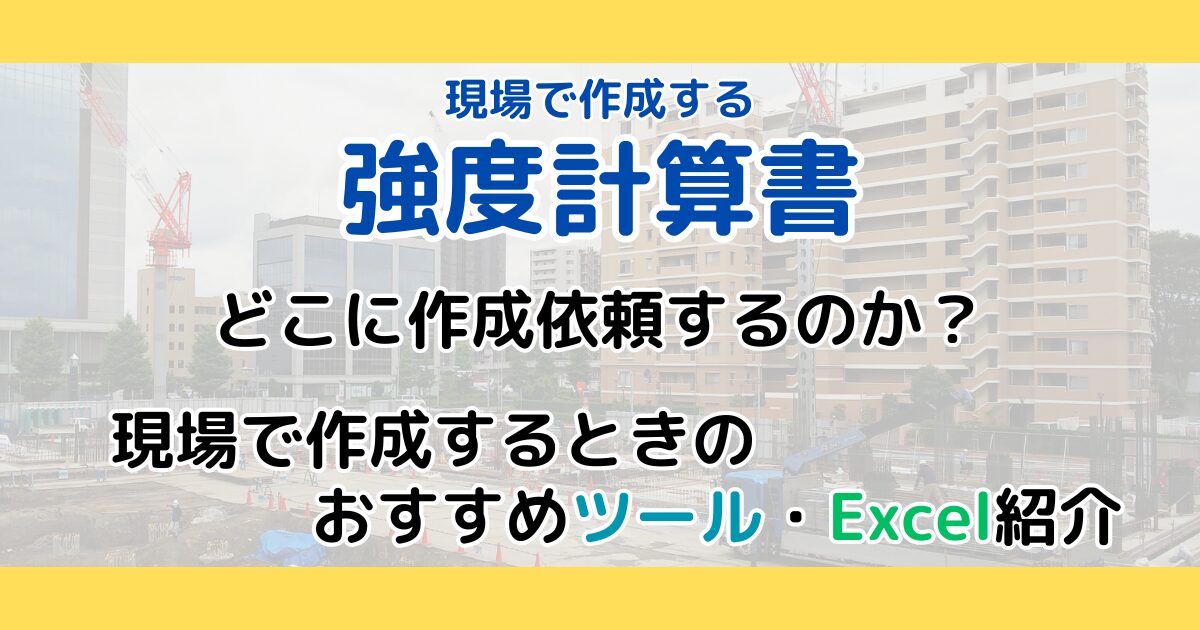

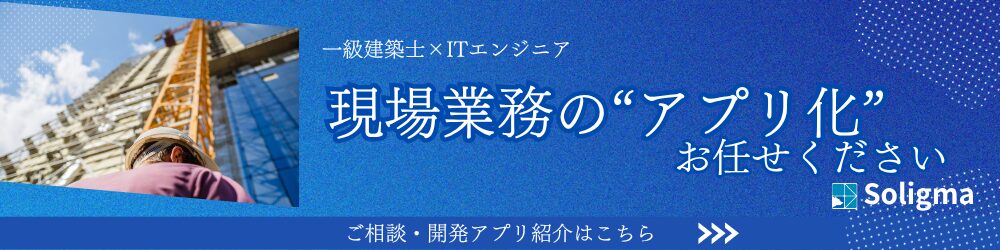
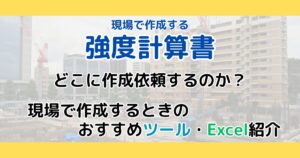
コメント